現代人を蝕む不健康現象②「口呼吸」
みなさんこんにちは。学芸大学駅徒歩5分、パーソナルトレーニングSTUDIO BE FREEトレーナーの吉田です。
『現代人を蝕む不健康現象』と題してお送りしてきています。前回は「過呼吸」についてお話をしてきました。
今回は「口呼吸」について詳しく解説をしていきたいと思います。
目次
- ○ あなたは大丈夫?意外と多い「口呼吸」
- ・そもそも口は呼吸で使う器官ではない
- ○ 口呼吸がもたらす弊害
- ・口呼吸のデメリット① 過呼吸になりやすい
- ・口呼吸のデメリット② 虫歯、歯周病、口臭の原因になる
- ・口呼吸のデメリット③ 免疫力が低下する
- ・口呼吸のデメリット④ 姿勢が悪くなる
- ・口呼吸のデメリット⑤ 睡眠の質が悪くなる
- ・口呼吸のデメリット⑥ 顔の形が歪む
- ○ 睡眠時間無呼吸症候群は生活習慣病のリスクも高める
- ・まずは医療機関に相談しよう
- ○ まとめ
あなたは大丈夫?意外と多い「口呼吸」
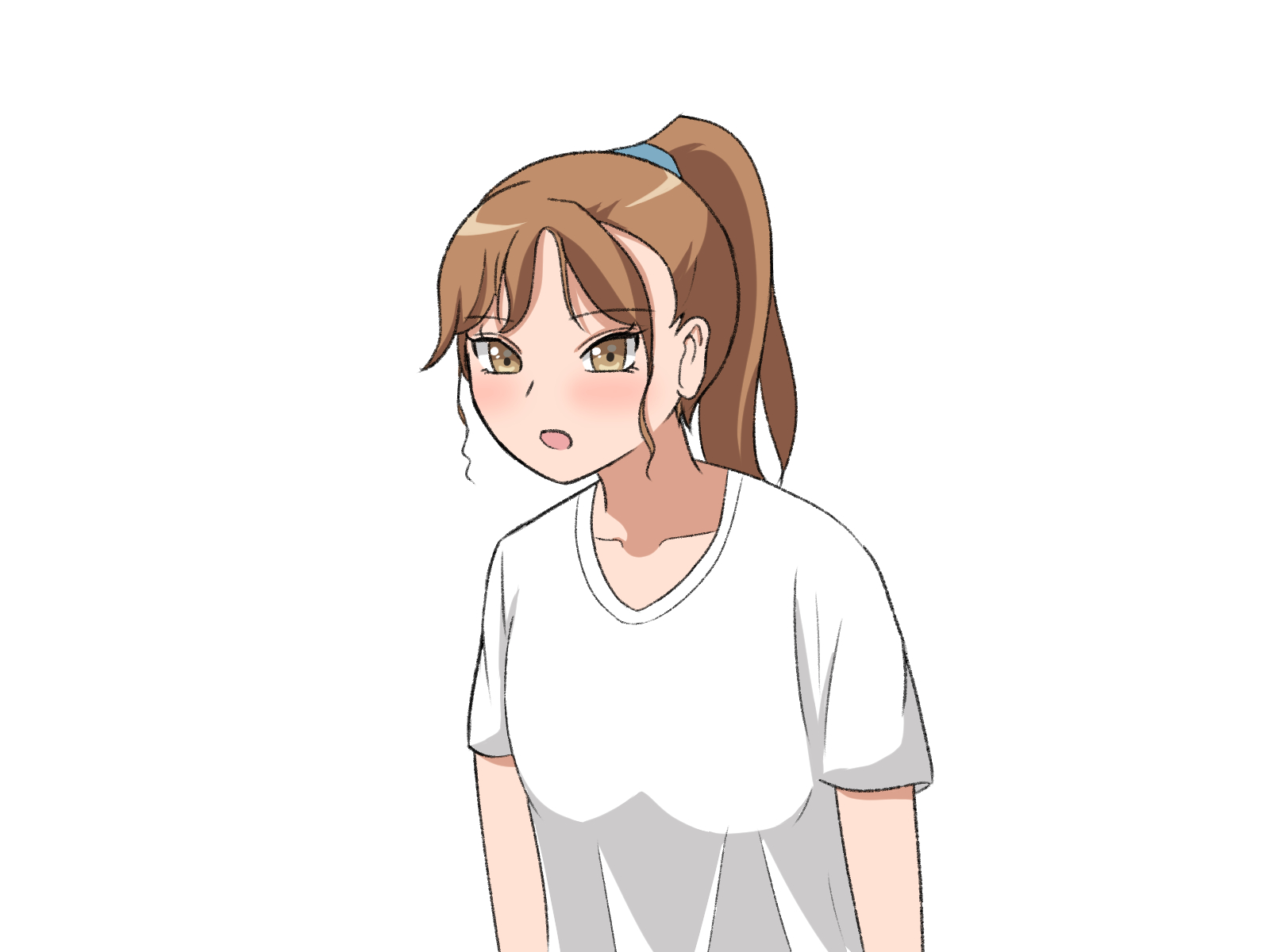
いきなりですが、テレビやスマホ画面を見ている時、無意識に口が開いていることはないでしょうか?または、ふと街角の窓ガラスに映った自分の顔を見た時、唇がうっすらと開いていて、前歯が見えるというご経験はありませんか?
もし、思い当たる節がある!という方がいらっしゃれば、「口呼吸」になっているかもしれません。口呼吸とは「口で息を吸う呼吸」を指します。正常な呼吸は「鼻で吸う」鼻呼吸が基本です。
そもそも口は呼吸で使う器官ではない
私たちの体に備わっている器官は、その働きによっていくつかに分類されています。
たとえば音を感知する「聴覚器」には外耳、中耳、内耳が、光の刺激を感知して脳に伝える「視覚器」には目が該当します。
では呼吸で使われる呼吸器はというと、「鼻、咽頭、喉頭、気管、気管支、肺」が該当します。口は呼吸器ではなく、胃や十二指腸、症候群、大腸などと同じ「消化器」に分類されているのです。
このように、私たち人間の体は鼻呼吸を前提にできています。そのため、口呼吸が慢性化すると体には様々なトラブルが出ると言われています。
口呼吸がもたらす弊害
では、具体的に口呼吸ではどのような弊害が出てくるのか?以下、口呼吸のデメリットを6つご紹介していきます。
口呼吸のデメリット① 過呼吸になりやすい

口呼吸のデメリットの1つめは「過呼吸になりやすい」ことです。過呼吸については旋回の記事で詳しくご紹介しましたので、ぜひ参照いただきたいのですが、現代人を蝕む不健康現象の1つです。
呼吸で吸った酸素を脳や筋肉の細胞に行き届かせるためには、血液中に一定濃度の二酸化炭素が必要です。吐く息の量に対して吸う量が多過ぎる「過呼吸」が常態化すると、血液中の二酸化炭素が減少し、結果として脳や筋肉への酸素供給が減ってしまい「細胞レベルの酸欠」を招いてしまいます。
口呼吸は鼻呼吸よりも多量の空気が体内に取り込まれてしまうため、過呼吸を招きやすくなります。「口呼吸を続けると脳に供給される酸素が約半分にまで減る」という研究報告もあります。
その結果、脳は慢性的に酸欠気味となり、
▪️慢性的な疲労
▪️集中力の低下
などを招きます。このような状態では仕事や勉強などのパフォーマンスも下がってしまうことが予想されます。
口呼吸のデメリット② 虫歯、歯周病、口臭の原因になる

口呼吸のデメリットの2つめは「虫歯、歯周病、口臭の原因になる」ことです。
口呼吸では口が乾き、唾液量が減ります。唾液は細菌を抑え、酸によって溶けた歯を修復するなどの役割を果たしています。そのため唾液が少ない状態になると、口内や喉の粘膜は無防備になり、口内環境が酸性に傾きます。すると、
▪️虫歯や歯周病
▪️口臭
などのリスクが高まってしまいます。
特に歯周病は歯茎だけではなく、体中に炎症が飛び散りやすく、そうなると交感神経系のスイッチが入りやすくなります。結果、体はストレス状態から抜け出せなくなり、様々な悪影響を及ぼす原因になります。
口呼吸のデメリット③ 免疫力が低下する
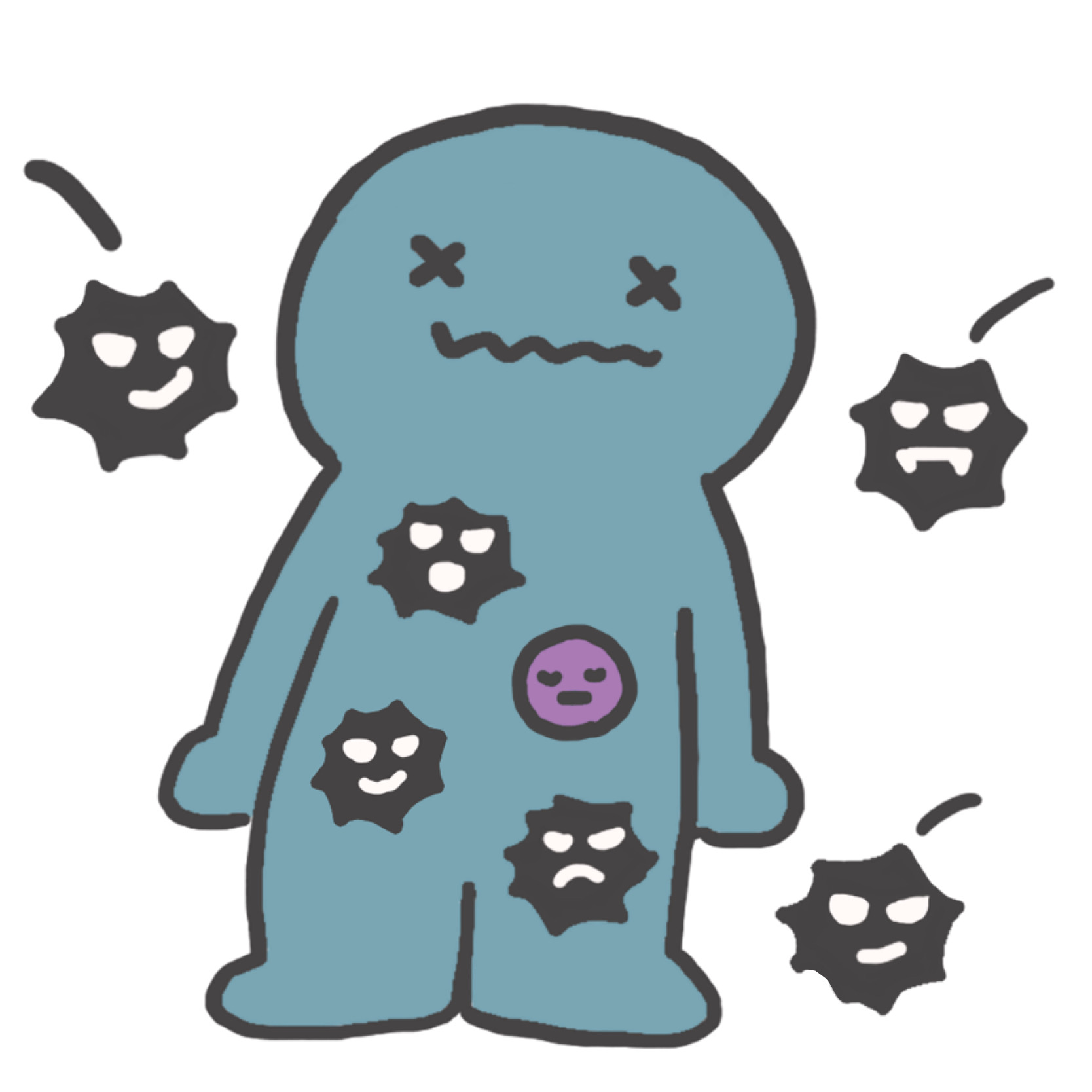
口呼吸のデメリットの3つめは「免疫力が低下する」ことです。
呼吸の基本は鼻呼吸。エチケットとして処理されることが多い鼻毛ですが、本来ならフィルターの役割を果たしてゴミが体内に入るのを防ぎます。
また、吸い込んだ空気を静脈で加温、粘液によって加湿し、湿気や鼻水でフィルターを通り過ぎた埃やゴミを防ぎ、細菌やウイルスもキャッチする働きもあります。
口呼吸では呼吸が鼻を通らないため、こうした鼻による濾過作用がなくなってしまいます。その結果、外気とともにゴミや有害な物質、ウィルス学芸大学駅直接体内に侵入し、免疫力も低下させる恐れがあります。
口呼吸のデメリット④ 姿勢が悪くなる
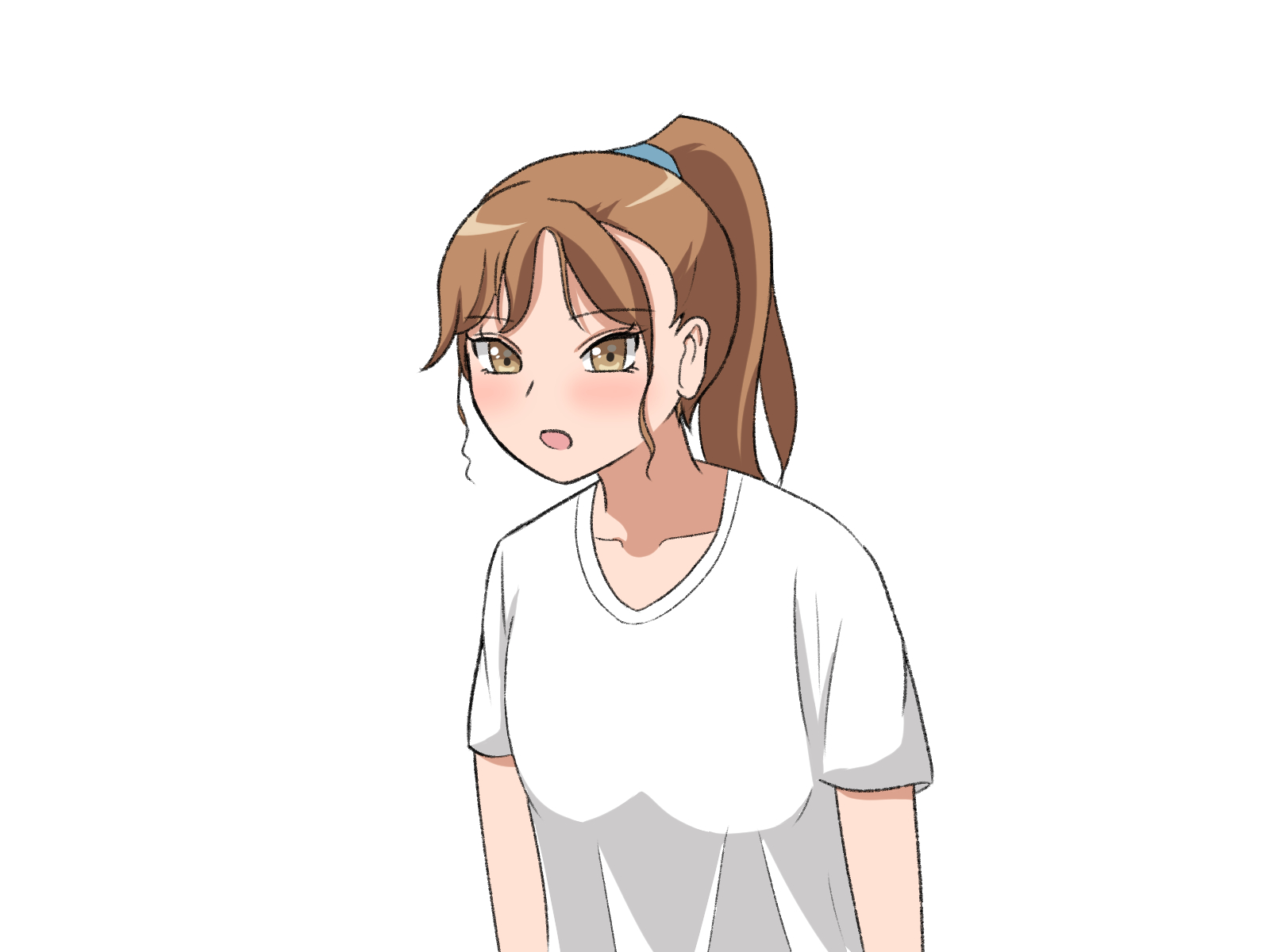
口呼吸のデメリットの4つめは「姿勢が悪くなる」ことです。
口呼吸が慢性的になると、顎が後退するため、気道が狭くなります。すると、そのままでは息苦しくなるため、無意識に頭部を前方に突き出して気道を確保するようになってしまいます。
頭部は5〜6kgとボウリングのボールほどの重さがあります。そのため、頭が前に突き出ると、その重みで背中が丸まり、「猫背」の原因となるのです。
口呼吸のデメリット⑤ 睡眠の質が悪くなる

口呼吸のデメリットの5つめは「睡眠の質が悪くなること」です。
睡眠中に口が開くことで舌が喉の方に落ち込んでしまい、気道を塞ぎ、
▪️いびき
▪️睡眠中時無呼吸症候群
のリスクを高めることが知られています。
また先述したように、口呼吸は過呼吸にもつながります。それにより、酸素が脳や筋肉にうまく供給できない「細胞レベルの酸欠」になれば、疲労の回復もできず、疲れが残ったまま翌日を迎えることにもなってしまいます。
口呼吸のデメリット⑥ 顔の形が歪む

口呼吸のデメリット6つめは「顔の形が歪む」です。これには「舌」の位置が大きく関係しています。
口が閉じている状態では、本来、舌先は上顎に触れています。これにより、上顎は内側から舌に押されることで支えられ、歯列を定位置に保たれるのです。
しかし、口呼吸が常態化すると舌が下顎に落ちてしまいます。すると、舌に内側から押されるはずの上顎は重力などの外部から顔にかかる圧力に負け、
▪️歯並びの悪化
▪️噛み合わせの不全に伴う顔の左右差などの歪み
の原因になります。
その他、顔の筋肉も下がり、顔や首がたるんだ老け顔になりやすくなることも。このように、口呼吸は美容の観点から見てもデメリットが大きいと言えます。
スポットとは、上の前歯の少し手前にあるやや隆起した箇所。ここに舌先が触れているのが健康的な状態である。
うっかり口が開いてしまうのは顎の筋肉が弱いせい、というのは間違いで、舌の位置が間違っているのが原因である。口が閉じている状態では、本来、舌先は「スポット」と呼ばれる正しいポジションに触れている。スポットとは、上の前歯の少し手前にあるやや隆起した箇所。ここに舌先が触れているのが健康的な状態である。
睡眠時間無呼吸症候群は生活習慣病のリスクも高める
先ほど、口呼吸で眠ると舌が下がりきって気道を塞ぎ、睡眠時無呼吸症候群になりやすくなるとご紹介しました。
この睡眠時間無呼吸症候群は生活習慣病とも密接に関連することがわかっています。実際、睡眠時無呼吸症候群を有する人は、健康な人と比べて高血圧のリスクは約2倍、また心不全は約3倍、脳卒中は約3〜5倍もの多さで発生するという報告もあります。
まずは医療機関に相談しよう
このように、睡眠時無呼吸症候群は命に関わる病気のリスクをはらんでいますが、口呼吸以外にも
▪️肥満
▪️睡眠薬やアルコールの影響
▪️顎の骨格的な構造
▪️鼻炎やアレルギーなどの鼻の病気
▪️加齢
など、様々な原因があります。そのため、まずは専門の医療機関に相談していただくことをお勧めします。
まとめ
▪️口は胃や十二指腸、小腸、大腸などと同じ消化器であって、呼吸でメインに使われる呼吸器ではない
▪️人間の体は鼻呼吸を前提にできている。そのため、口呼吸が慢性化すると体には様々なトラブルが発生する。具体的には、
・過呼吸になりやすい
・虫歯、歯周病、口臭の原因になる
・免疫力が低下する
・姿勢が悪くなる
・睡眠の質が悪くなる
・顔の形が歪む
などのリスクが考えられる。
▪️睡眠時無呼吸症候群は口呼吸以外にも様々な原因がある。命に関わる病気のリスクも高めるため、医療機関への相談が必要
次回は「現代人を蝕む不健康現象」の3つめ、「体が迷子状態」をご紹介します。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

